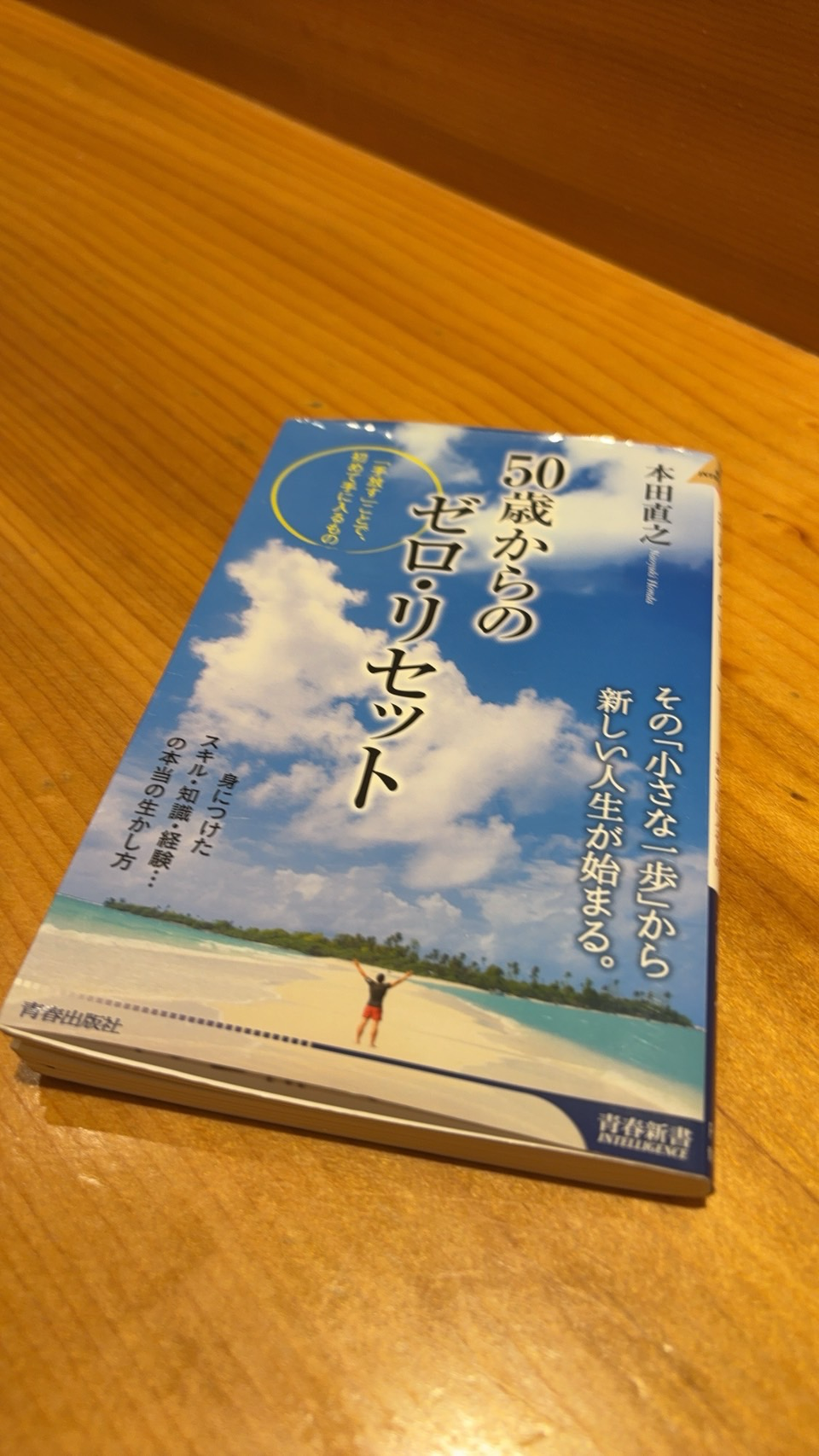「粋・丸新」 料理長 熊倉 誠さん
「粋・丸新」
所在地:福島県郡山市神明町15-4
Instagram: https://www.instagram.com/marusin_5/
「郡山・丸新五代目の転換点。“尖り”を超えた先に見えた景色」
明治期に創業し、100年以上の歴史を刻む郡山の老舗「丸新」。米屋から蕎麦屋、総合食堂を経て現在の姿へ――家業のバトンを受け取ったのが五代目・熊倉誠さんだ。東京での約10年の修業を終え、二十九歳で帰郷。自負と焦りを抱えながら業態転換を進め、震災やコロナをくぐり抜ける過程で価値観は大きく反転した。「自店だけでは東京に勝てない。仲間とチーム戦で挑む」。地域の食を編集し直す挑戦は、いまも続く。
受け継ぐ必然、変える決断
熊倉さんにとって「継ぐ」ことは、選択ではなく空気のように当たり前だった。周囲が大学に進学する頃、「修業に行きなさい」と背中を押された。
丸新が生まれた背景は明治時代から始まり100年以上続いている。創業者は、新潟の米屋の次男だった。長男が家を継ぎ、次男とか三男は必然的に家を出される時代だった。その後、次男である創業者は郡山に辿り着き、米屋からスタートした。
しかし新参者には厳しい土地で米屋は難しく、日銭を求めて蕎麦屋に転じる。戦後、祖父母が「丸新食堂」を立ち上げ、父の代では宴会や会合を受ける総合食堂へと拡張した。そして、熊倉さんの代で今の業態に転換した。丸新は、時代と共に姿を変えながら生き延びてきた“食の変幻”の歴史そのものだった。
東京で修業した熊倉さんが戻ったのは29歳。銀座の飲み屋の主や経営者からも一目置かれ、成功体験を携えていたが、それが故の“勘違い”もあった。今のように情報がない時代で、しっかりと地元に戻ってから1、2年腰を据えてからスタートしていればもう少し物事を見極められたが、帰ってすぐに店を新しくしたという気持ちが強かった。
丸新を、料理屋として洗練させたい――情熱のままに改装・メニュー刷新を進めた。設計者やデザイナー探し、器の選定、資金調達。学びのないまま飛び込んだ現実は想像以上に苛烈で、業態転換は痛みを伴った。店のコンセプト・業態を変えることで、通い続けてくれた近所の客の居場所が失われる懸念、地元での信用の築き直し。だが、「自分がやらなければ誰がやる」という覚悟が背を押した。
時代が変わる、商いが変わる
町の商店街がしぼみ、飲食店の継続は一握りの努力家に限られる時代になった。バブル期の「普通にやれば儲かる」から、「相当頑張らないと続かない」へ。熊倉さんは、食材の目利きや調理技術に磨きをかける一方で、“見せ方”と“つながり”の重要性を痛感していく。だが三十代の自分は尖っていたと振り返る。
29歳で地元に帰り、自分の店を出すと長く住み育った街でも「新参者」の扱いだった。田舎でも10年以上離れると街もだいぶ変わっており、その中で新しい店を出す為、「認知」をいかに取るか、そのためには「尖らないといけない」と思っていた。朝から晩まで働き、周りと共存していくというよりは、自分が頑張らないといけないと孤軍奮闘していた。自店を成長させる為には周りは全てライバル、言い方を悪くすれば敵だと思っていた。自分のやり方に固執し、従業員にも厳しかった。三十代は寝ないで市場の競りに参加し、周りの店より良い食材を仕入れる、良い生産者を自分が優先的に確保する――そんな競争の論理で走り続けた。
転機は2011年の東日本大震災だ。積み上げてきた常識がゼロに戻り、生産者やお客の「支え」によって自分の仕事が成り立つ事実を突き付けられた。支援の手に励まされる一方で、名のある料理人としての責任や葛藤も知った。四十代の10年間は“価値観の反転”の時間だったという。勝つために尖るより、恩に報いるために磨く。個の腕を競うより、周囲の力を生かして結果を出す。「恩返し」に軸足を移すほど、心は軽く、道はクリアになった。
学び直す五十代――パーツを交換し続ける
五十代に入り、熊倉さんは「一兵卒に戻って学び直す」姿勢を意識されている。多様な専門家が集う学びの場(Honda Lab.)に参加し、経営や地域観光まで、外の知恵を貪欲に吸収する。田舎で全てを自力で賄うのは難しい。だからこそ、知恵のネットワークにアクセスし、自分の中の“パーツ”を随時交換していく。食の表現だけでなく、暮らし方も変わった。走る、体を絞る、平日の酒を控える――行動が変われば、語る言葉も変わる。影響は厨房にとどまらない。
五十代に入り、「尖り」から「恩返し」へと意識が変わった事で、周りの五十代を見た時に危機感を覚えた。若い世代から気軽に話しかけてもらえない先輩たちを見た時に、若者に対して、ああでもないこうでもない、自分たちの過去はこうだった、と話す姿を見て少し寂しく思えた。そして、コロナ禍にナオさんの書籍「50歳からのゼロ・リセット」を読みこれだと確信を得た。
ラボに入る前、イトケンさんがナオさんをお店に連れてきてくださり、初めてお話しする中で「この人だ!」と感じた。書籍の中にもあったが、若い世代にも気軽に声をかけてもらえる存在、50歳だからこそ一兵卒になってもう一度学びなさなければいけない、という内容が心に響き、自分もそのような存在になりたいと思った。ラボに入る前から、自分自身がサボってきた訳ではないが、ナオさんやメンバーの頑張る姿を見ていると、まだまだ自分はサボっているのではないかと思えるようになった。そう思えたからこそ、自分の尖っていた部分が落ち着き、自分のことを俯瞰して見れるようになった。その考え方、姿勢が確信に変わった。
各年代で考え方が変わり、今は子供の頃の純粋な自分に戻ってきた。自分の息子が店に入ってきたことも大きかった。自分の息子ができないという事は、父親である自分が悪いと言えるようになった。(他責から自責へ)今では、若い世代からも学ばせてもらうという姿勢になった。これまで張り詰めていたものから解放されたのか、学ぶ側に戻った時に心地よさを感じた。震災という経験がなければ、尖ったままだっただろうし、嫌な人間になっていたと思う。変われたからこそ、同じような経験をしている人、悩んでいる人を見ると理解できるようになったし、かける言葉・関わり方が変わった。
考え方、行動の変化は言い換えると、自分の中の「パーツ交換」だと思っている。自分の本体は「進化し続ける装置」であり、学びは自分の劣化したパーツを新しいパーツに取り替える作業である。いつからだって変わることができる。ナオさん自身がお手本を示してくれている。いろんなところに出向き、いろんな人と関わり、常に自分をアップデートされている。自分は、歳を重ねてきているので人から刺激をもらわないと変われないと思っている。Honda lab.が刺激をもらえている場であり、感謝している。
劣等感から生まれたチーム戦――
東京で修行を終え、福島に帰ってきた頃から、「劣等感」は常に持っていた。東京や京都と肩を並べる存在・地域でありたいと想い続けてきた。当初は、ここが負けている、勝っているばかりを意識してきたたが、今は来て頂いたお客様にどうやって満足してもらえるかを考えている。その為には、常に学び続けないといけないし、自分より年齢や経験が浅くても素晴らしい料理・価値観・心構えを持っている料理人はいる。彼らに素直に「教えてください」と言えるような自分でいたい。自分が変わり、周りから「この人面白いな」とか、「この人といつか一緒に飲んだり、料理をしたいな」と思ってもらえるようにしないといけない。こう思えるようになったのは、ナオさんと初めて行ったサウナで、緊張している自分に声をかけてもらいアドバイスを頂いたのがきっかけだ。
「活躍している料理人の年齢はどんどん若返っており、自分が歳を重ねていく中で常に若い料理人と対峙していかないといけない。そこに五十代のクマが太刀打ちするには、今まで磨いてきた技術プラス、若い料理人から学んでいろんなことを取り入れたかないと無理だ。」
by ナオさん
震災を乗り越えたというのが、僕らのアイデンティティだ。変われたということは、これからもどんどん変われるのだと確信している。
これらの「学び」は、地元に還元して初めて価値になる。仕入れ先の共有、ナレッジの共有、若手とのネットワークづくり。月謝を払って学ぶコミュニティに馴染みの薄い地方では、まず自ら身銭を切る背中を示し、同じ熱量で外へ出る仲間を探す。「一つの料理屋のコンテンツだけでは東京に勝てない。仲間とチーム戦で戦う」。郡山・福島・山形・仙台を面でつなぎ、訪れた人が“一度にいろんな体験(食・文化・人)ができる”場づくりを構想する。Honda.lab.の学びを活かし、福島・東北で小さなラボのようなコミュニティを作りたいと思っており、今少しづつ実験中である。アウトプットは一人称ではなく複数形で――それが熊倉流の地域戦略だ。
熊倉さんのこだわりや、Honda lab.に入っての変化・PX
「常に料理人である事」
どんなに変化をしていっても、基本「料理人」である事はブレないでいる。毎日朝ちゃんと起きて、仕込みにも手を抜かない。当たり前のことを当たり前に行う。当たり前を怠ると、料理人としてのセンスが落ちていくと思っている為、そこはブラさない。これからも、いろんな人と出会い、いろんなことを学んだとしても料理人であることを忘れない。自分のストロングポイントをおろそかにせず、自分が出来ない事には手を出さない。
写真:「I.N.U.飯田橋 × 丸新」 ラボメンバーとのコラボイベント
「手本から学ぶ」
Q.日々現場を離れられない環境の中で、合宿やイベントに参加されていますが、どのように時間をやりくりされているのでしょうか?
時間のやりくりが一番難しいと考えていたが、自分より多忙な環境下で時間をやりくりしている先輩がいた。イトケンさんだ。イトケンさんにどのように時間をやりくりされているのかと聞いた際、「弾丸ですよ」と教えて頂いた。今までは無理だと思っていたことも、実践しているお手本があるので無理だと思わなくなった。逆に限られた時間なので、集中して学びを得ようとするので良い効果が出ている。パワフルでガンガン突き進んでいくイトケンさんや、穏やかで人に害を与える事を一切言わない仏のような岩井さん、自分の身近には素晴らしいお手本がたくさんある。彼らに影響されていろんな事を自分に取り入れ、進化させている。料理も同じような事が言える。言い方悪く言えば、料理も模倣なところがある。新しい料理に出会い、そのエッセンスを自分に取り入れ自分なりに進化させていく。
「曖昧さを持たせる伝え方」
Q.熊倉さんと話す中で、言葉選びや伝え方が特徴的だと感じましたが、何か気をつけている事はあるのでしょうか?
自分は国語力がなく、料理の作り方もしっかり一から十まで話せなく、どこかが欠落していると思っている。単語やニュアンスで伝えてきたのもあり。意識してきたのは、ダラダラと解説をするのではなく、短い単語やニュアンスを選び伝える人間になった。以前は、“言い切る(主張)”伝え方をしていたが、受け取り手の解釈は人それぞれであり、理解してくれる人もいれば、そうは思わないという人もいる。また、若い時には先輩方に食べにきてもらう事が多く、その言い方が上から目線に受け取られることもあり、良くない側面があることに気づいた。 ”言い切る事“も大事だと思っているが、少し曖昧さを含めた伝え方をする事で、受け取り手が想像してくれる。それぞれの解釈があって良いし、それぞれの解釈を楽しんでもらう事が大事だと思っている。新規で来てくださったお客様に料理を通して、丸新、福島、東北を好きになってもらい、また訪れてもらうような場づくりを心がけている。
「一石二鳥、さらには一石三鳥」
この言葉が好きだが、例を出せば最近減量に成功した。ラボに入ったことで健康の意識はさらに高まった。ラボには健康意識の高い方が多く、「ラボに入る」→ラボに入ると「走る」→走ったら「痩せる」。一石三鳥だ。68kgあった体重は今では62kgまで下がった。影響されやすい性格で、最近のナオさんの体型を見たら自分もそうなりたいと思えた。今では毎日走るこ事と腹筋を継続している。ナオさんが平日酒飲んでないという話を聞き、自分も平日飲むのを辞め、週末及びどこか出かけた時のみにしている。
福島という“多文化県”を編集する
Q.熊倉さんが思う郡山・福島の魅力はなんですか?
自然が豊かで食材が多彩、人柄は温かい。震災を耐え抜いた生産者の気迫は圧倒的で、胸を張れる名産が身近にある。福島は会津・中通り・浜通りと文化圏が大きく異なる“多文化県”でもある。馬刺し一つとっても地域によって意味が違い、祭りも食習慣も多様だ。「統一感がない」と見える特性を、熊倉さんは“編集の余白”と捉える。温泉、旅のコンテンツ、食、人――揃っているのに、我々が活かし切れていないだけ。見せ方が変われば、福島の“楽しさ”は身近な海外になる、と思っている。
「託された思い・モノを次へ繋ぐ」
Q.困難な状況や調子がでない時に何か心がけている事は何ですか?
自分の仕事は生産者さんや従業員さん、支えてくれている人達が僕に託してくれたからこそ出来ている仕事なので、その気持ちを奮い立たせている。自分が何かを生み出したとか、自分がお金を稼いでいるとか、自分一人でやっている商売、という事では無い。この考えが根底にある。支えてくれる人がいて、それを商品化しているだけなのだ。一生懸命作っている人がいるから自分の仕事ができている。そこを適当に考えたり、サボったり、やる気が無い姿勢を見せる事は失礼である、という気持ちを常に持つようにしている。震災の経験と比べると、苦労したからこそ今は幸せであると思える為、大抵の困難や苦難に対する免疫ができている。
自分一人が作った店では無いので、先代達が繋いでくれている。祖父は戦争乗り越え父に繋いでくれた。それぞれの先代は大変な時代を乗り越えてきて後世に繋いでくれている。先代達の想い、今、自分を応援してくれている人達の想いをいかに後世に繋いでいくか、その為には今どうすべきか。頑張るしかない!
結び
受け継いだのは歴史だけではない。繁忙の厨房で擦り減った矜持、震災で反転した価値観、五十代で始めた学び直し。熊倉誠という料理人は、「尖り」を脱ぎ捨て、「恩返し」を纏った。その歩みは、郡山の食を今日も静かに、しかし確かに更新している。変化は続く。なぜなら彼は知っているからだ――“変われた”という実感こそ、明日を変える最良のレシピだと。
今後もHonda Lab.メンバーへのインタビューを実施していきます。お楽しみに!
interview by @SHOTA @みぃ @Norihito
Text by @SHOTA (松山 将太)